![]() 喫茶店『Mute』へ
喫茶店『Mute』へ
![]() 目次に戻る
目次に戻る
![]() 前回に戻る
前回に戻る
![]() 末尾へ
末尾へ
![]() 次回へ続く
次回へ続く
![]()
きらめき中央病院の1階にある喫茶室のお手洗い。
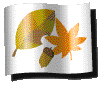
藤崎さんはあたしに訊ねたの。
「虹野さんは、森くんが事故に遭う少し前まで一緒にいたのよね?」
「ええ」
あたしはうなずいた。
そう、あれは去年の11月の……、確か休日明けだったから、4日だったのよね……。
秋も終わりって頃で、すっかり日が暮れるのも早くなってたのよね。サッカー部の練習が終わる頃には、もうあたりは薄暗くなりはじめていたの……。
1年のみんなは、ボールの後片づけとかグラウンド整備とかしなくちゃいけないから、先輩のみんなよりも終わるのが遅くなっちゃうのよね。
マネージャーのあたしとしては、それだけ頑張ってる1年のみんなの励みになれば、なんて思って、時々差し入れを作ってるの。その日も、家庭科室を借りて、おにぎりを握って持っていったのよね……。手が汚れてても、そのまま食べられるように、サランラップに包んで。
みんな、喜んでくれて、それがまた嬉しくって、ついつい、いっぱい作っちゃうのよね。
あの時も……。
「お疲れさま! はい、差し入れよ」
あたしがお盆に載せたおにぎりを差しだすと、みんながどやどやと集まってくるの。
「サンキュー」
「いいっすねぇ、家庭の味ってやつっすか?」
「やだ、森くんたらぁ。よし、お茶つけてあげるね」
「あ、虹野さん、俺も……」
「いいわよ。はい」
あたしがお茶を注いで主人くんに渡したら、主人くんったら、
「きっと虹野さんっていいお嫁さんになるよね」
って。やだな、もう。
「やだ、なに言ってんのよ」
あたし、慌てて後ろを向いたの。だって、頬っぺたがかぁっと赤くなっちゃったんだもの。
「こら、主人。マネージャーが困ってるだろうが」
「あ、そうじゃないの、違うんだってば! あーん、もう!!」
「さ、早く帰ろうぜ」
「そうっすね。あれ、マネージャー?」
部室から出てきた森くんが、待ってたあたしを見て訊ねたの。
「あ、森くん、主人くん。着替え終わったのね」
「どしたんだ?」
「うん、もう真っ暗でしょ? なんとなく一人で帰るのって怖くて……ね」
うん。ホントにそれだけなのよ。それだけなんだってば。
主人くんは自分の鞄を肩にかついで言ったの。
「そうだね。じゃ、俺が送っていってやるよ。確か同じ方向だったもんね」
「じゃ、俺は一人寂しく帰るっす。お幸せに〜」
「何よ、それ。そんなんじゃないんだってば」
あたしは、慌てて言うと、主人くんの顔を見た。
主人くん、苦笑してるだけみたい。迷惑じゃ、ないよね? よかった。
帰る方向がまるで逆な森は一人寂しく道を歩いていた。
もっとも、彼が今歩いているのは国道沿いの賑やかな歩道で、ちょうど週末ということもあって結構人通りは多かった。
「独り身に、冬の風が冷たいねぇ。ちょっくらゲーセンでも寄って暖まるかな」
彼はそう呟いたものの、ポケットを探ってそれを断念した。
「ううっ、貧乏人はつらいっす。がっ……くり」
森が肩を落とした、ちょうどそのとき、誰かが思いっきり体当たりしてきた。
ドシン
「きゃっ」
かわいい悲鳴が聞こえた。森は立ち上がると、尻餅をついているその娘の方を見た。
「大丈夫っすか」
「ご、ごめんなさ……」
その少女は謝りながら彼の顔を見て凍り付いた。
夜、いきなりぶつかった相手がドレッドヘアな奴だったから無理もない。
彼女は顔をひきつらせて、口をぱくぱくさせていた。
一方、森はもうこういう反応には慣れっこになっていた。肩をすくめて、そのまま行き過ぎようとしたが、ふと何かが気になって振り向いた。
ほっとして立ち上がろうとした少女が、また凍り付いたように動きを止める。
(……うちの学校の制服じゃねえか。それで、か)
森は納得した。にっと笑って言う。
「さっさと帰った方がいいっすよ。このあたりは怖いお兄さんが徘徊してることが多いっすから」
「……できません」
小声で、それでもはっきりその少女は言った。
「え?」
「だって……だって……」
不意にその少女は泣きだした。
森は慌てた。
「だって、ひっく、ムクがどこかに行っちゃったんだもの。見つけるまで……帰れないの……」
「ムク?」
しばらく話を聞いて、森はやっとムクが犬だということがわかった。
「……わかったっす。手伝うっすよ」
「え? で、でも……」
「困ってる女の子を見たら親切にしてやれっていうのがばあちゃんの口癖だったっすよ。それに、俺、犬好きっすから」
「そ、そうですか?」
森は愛からムクの説明を受け(愛「これくらいの大きさで、毛が長くて……、色は焦げ茶色の、とってもかわいい子なんですよ。ちょっと人見知りするみたいなところがあって、知らない人にはすぐ吠えるんですけど、私がめって叱ったらちゃんということ聞いてくれるんですよ」森「ムクの話になると、饒舌っすね」)森は辺りを見回した。
彼女の話によると、公園に散歩に出て、ちょっと目を離した隙に見えなくなってしまったらしい。
「じゃ、俺あっちをさがしてみるっす」
「す、すみません……」
森はドレッドヘアを風になびかせて走り出した。
「こっちにはいないかな?」
森は辺りを見回した。
と、彼の目に茶色の毛玉が写った。
「あ。こいつか!?」
彼はかがみ込んで呼んでみた。
「ムク!」
その毛玉はぴくっと動き、こっちの方を見た。かと思うと、そのまま車道に飛び出す。
「あ、こら…、やべ!」
ブォーッ
大型のダンプカーが疾走してくる。その強烈なライトに照らされたムクはおびえて動きを止めた。
「ちっ」
森はガードレールを飛び越え、車道に駆け下りた。
(間に合わねぇ! ええぃ!)
彼はジャンプしてムクに飛びついた。いつも練習しているセービングの要領である。
つかむと同時に、アスファルトに身体が落ちる。痛みをこらえつつ、ムクをそのままもと来た方に投げつける。
キャン
悲鳴のような声を上げながらムクは歩道に放り上げられる。そして、そのまま走り去っていった。
彼が覚えているのは、そこまでだった。
《続く》