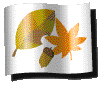喫茶店『Mute』へ
喫茶店『Mute』へ
 目次に戻る
目次に戻る
 前回に戻る
前回に戻る
 末尾へ
末尾へ
 次回へ続く
次回へ続く

沙希ちゃんSS 沙希ちゃんの独り言
第

 話
話
アレ・キュイジーヌ 前編
※今回は、いつもと型式を変えてお送りしています。

10月15日、日曜日。
私立きらめき高校では、文化祭の2日目を迎えて、普段とは違った賑わいを見せていた。
いつもは黒い詰め襟と白と青のセーラー服ばかりのここも、今日ばかりは様々な色で埋めつくされているようだった。
今も、プログラムを片手にした私服の少年少女の一団が、声高に話をしながら、校門を入っていく。もの珍しげな様子から見てきらめき高校の生徒ではないようだ。何となく幼い感じを受けるところからみて、中学生だろうか?
「今日の見物は、なんてったって、3on3大会だろ?」
「そうそう。やっぱ、これだよなぁ。何時からだ?」
「予選が10時から……って、もう始まってるじゃねぇか!」
「そんなの決勝だけ見ればいいじゃない。第一、私達は遊びに来たんじゃないのよ」
おかっぱ頭の少女がたしなめるようにいうと、その後ろの青い髪を一本のおさげにして垂らしている少女が大きくうんうんとうなずく。
「千晴ちゃんの言うとおりよ!」
「虹野先輩、あなたの言うことも多分違うと思う……」
おかっぱ頭の少女は、額を押さえながら呟いた。青い髪の少女は腕を組んで、当然のごとく言い放った。
「お姉さまの出る“きらめき高校料理の鉄人”を見るに決まってるじゃない!」
「……やっぱり」
全員が大きなため息をついた。
 「外井」
「外井」
ルノ・マッティーニの豪奢な衣装に袖を通しながら、伊集院レイは声を掛けた。
「は、ここに」
伊集院専用控え室のドアの外から、即座に返事が戻ってくる。
レイは鏡に向かって髪をときながら訊ねた。
「準備はどうなっている?」
「すべて順調でございます。懸案になっておりましたトリュフも、フランス政府に専用機を用意させまして、今朝到着いたしました」
「そうか」
満足げにうなずくと、レイは立ち上がった。
「この僕が主宰するのだ。すべて、完璧に、な?」
「心得ております」
ドアの向こう側で、外井は深々と一礼した。
 「沙希ぃ、元気ぃ? この朝日奈夕子ちゃんが励ましがてら、インタビューに来たぞぉ!」
「沙希ぃ、元気ぃ? この朝日奈夕子ちゃんが励ましがてら、インタビューに来たぞぉ!」
“鉄人控え室”という紙が貼られた、普段は女子更衣室に使われている部屋を、朝日奈夕子はマイクを片手に開けた。
その後ろから、“放送部”の腕章をつけ、テレビカメラを持った生徒がついてくる。
「あ、……ひなちゃん?」
椅子に座っていた沙希は振り返った。夕子はぎょっとした。
「さ、沙希?」
「……うん」
夕子がぎょっとするのも無理はなかった。いつもの元気溌剌とした沙希とはかけ離れた少女がそこに座っていたのだ。
目の下には隈までつくっている沙希は、ぎこちない笑顔を浮かべた。
「どうしたの、ひなちゃん?」
「どうしたのって、えっと、その……」
夕子は頭を一振りして、任務を思い出した。
「取材よ取材。ほら、カメラあっち。これ、生放送だからね」
「え? ……そうなんだ」
「どうやら鉄人、ずいぶんと緊張してるようですねぇ」
とりあえずカメラに向かってフォローを入れながら、夕子はマイクを沙希に向けた。
「いよいよ本番まであと僅かとなりましたが、調子はどうですか?」
「……え?」
「だから、調子はどうかって?」
「お銚子はお酒を入れるものです」
「……おいおい」
思わず突っ込んでから、夕子は親友の顔に戻った。
「ちょっと、マジ大丈夫?」
「……大丈夫」
沙希はそう言って立ち上がろうとしてよろめいた。
「きゃ、沙希!」
とっさにその沙希を支えると、夕子はカメラに向かって言った。
「鉄人、これはかなりのプレッシャーを受けているようですね。現場からは以上です。本部の早乙女くん、お返しします!」
 「はい、朝日奈リポーターでした」
「はい、朝日奈リポーターでした」
放送室では、それを受けて早乙女好雄がマイクに向かっていた。ちなみに、きらめき高校内の各所にあるモニターから放映されている、この「特別報道番組 もっときらめき文化祭」という生番組は、一応放送部の出展作品という扱いである。
「それにしても鉄人虹野、大丈夫でしょうか? 解説の館林先生?」
「ま、なるようになるでしょ。鉄人はプレッシャーに弱いのが最大の弱点って言えば弱点だからねぇ」
好雄の隣に座っている2年E組担任の館林晴海は、カメラ目線で微笑んだ。
好雄が訊ねる。
「しかし、ここまで来てまだ挑戦者が誰なのか、我々にもまったく知らされていないんですが、先生は何か御存じでしょうか?」
「それは言えないわよ」
カメラ目線のまま、キッパリ言う晴海。
「先生っていう職業は信用第一ですからねぇ」
「はぁ……」
納得できない、という顔で、一応うなずく好雄。そこに一枚の紙が差しだされる。
「え? もう俺の出番か? わかった。 えー、番組の途中ですが、私、早乙女好雄は今から3on3大会に出場するために行かねばなりません。女生徒のみんな、この愛の伝道士、早乙女好雄に応援ヨロシク! それじゃこれにて、「もっときらめき文化祭」第1部終了だぜ!」
ガラス窓の向こうの放送部員がミュージックを流し始める。それを聞きながら、好雄はスタジオを出ると体育館に向かって走り始めた。
しかし、好雄にとって不幸なことは、彼のチームメイトが芹澤勝馬と伊集院レイであることだった。女生徒の視線はこの二人に釘付けになってしまい、好雄はこの日もまた、誰にも声を掛けてもらえない結果に終わる。
 伊集院専用控え室の中から、レイが声をかけた。
伊集院専用控え室の中から、レイが声をかけた。
「外井、そろそろ3on3大会の予選だな?」
「は。既に“影武者レイくん2号”は配置についております」
「そうか」
レイは、マジックミラーになっている窓から、体育館の方をちらっと見た。その眉が微かに曇ったのは、扉の外にいる外井にしか判らなかった。
(レイ様……、あと1年半の御辛抱でございます)
外井は、レイには見えないと知りつつも、深々と頭を下げるのだった。
伊集院家の当主となるべく定められたレイ。本来は、そのレイを身代わりとなって守るために存在する数人の“影武者”だが、今はレイの秘密を守るために、主に体育などの時に、文字通りレイの身代わりとなっているのだ。
今日の3on3大会も、その影武者の一人がレイ自身の代わりに出場しているというわけだ。
影武者が表に出ている間は、レイ自身が姿を見せるわけにはいかない。というわけで、レイは控え室でじっとしているしかなかった。
と。
トントン
不意にノックの音がした。思わず身を固くすると、レイは振り返った。
「外井か?」
「いいえ。古式でございます」
その声に、レイは苦笑した。
「いつもいつも、まったく」
「失礼いたします」
ドアを開けて入ってきたのは、古式ゆかりだった。後ろで、外井が丁重に頭を下げているのが見える。
「古式くん、勝手に入ってこられては困るな」
レイは手を振って外井にドアを閉めさせると、肩をすくめて椅子に座るように促した。
「申しわけありません」
口ではそう言うものの、にこにこしてまったく悪びれた様子のないゆかりに、レイも微笑んだ。
「君には困ったものだ。それにしても、虹野くんの助手だろう? 一緒にいなくてもいいのかね?」
「はい。虹野さんには秋穂さんがついていて下さいますし、わたくしが一緒では、よけいに緊張してしまうかもしれませんので」
丁寧に答えるゆかりに、レイは真面目な顔になった。
「先ほどの放送は見ていたが……、虹野くんは大丈夫か?」
「そうですね……」
ゆかりは頬に手を当てて考えると、にこっと笑った。
「それが大宇宙の真理ですわ」
「……それはちがうぞ、ゆかりくん」
額を押さえるレイであった。
 「虹野先輩、大丈夫ですか?」
「虹野先輩、大丈夫ですか?」
鉄人控え室。
秋穂みのりは、心配げに沙希の背中をさすっていた。
「ありがとう、大丈夫よ」
およそ大丈夫には見えない顔色で答える沙希。
「大丈夫には見えません! 先輩、髪の色よりも青くなってますよ!」
「そ、そうかな?」
「そうですっ。昨日、ちゃんと寝たんですか?」
「う、うん……1時間くらい」
小声で答える沙希。
みのりは、ちょっと考えてから立ち上がった。
「みのりちゃん?」
「虹野先輩、やめちゃいましょう!」
「え?」
「こんな状態でお料理なんて無理です! 私、本部に行って、今日の勝負をやめてもらうように言ってきます!」
「それは、いけません」
もう一つの声がして、ドアが開いた。
沙希はそちらをみて、弱々しい笑みを浮かべた。
「未緒ちゃん、来てくれたんだ。ありがとう」
「如月先輩!」
そこに立っていたのは、如月未緒だった。
みのりは、未緒にくってかかった。
「どうしてダメなんですか!? 虹野先輩、こんな状態なんですよ!!」
「答えは、沙希さんが一番よく知ってるはずです。そうですよね、沙希さん?」
未緒は、緑色の瞳を沙希に向けた。
「……うん」
沙希はうなずくと、鏡に向き直った。
「判ってる。判ってるんだけど……」
「にじのぉ!」
不意に怒鳴られて、思わずびくっとする沙希。
「え?」
未緒の後ろから、ひょこっと変な髪型の少女が顔を出した。怒鳴ったのはその少女らしい。
「見晴……ちゃん」
「かぁ〜っ、情けない。それでも我がライバルかぁ?」
見晴はぺちんと額を叩いた。
「ご、ごめんなさい」
「ふぅ」
思わず頭を下げて謝る沙希を見おろして、見晴はひとつ息をついた。そして、右の髪留めを外した。
ぱさっ、と、右の輪になっていた髪が解けた。
「え?」
「これ、貸してあげるから」
そう言うと、見晴は沙希の髪にその髪留めを付けた。
「見晴ちゃん?」
「ちゃんとやんないと、主人くんはもらっちゃうから。ね?」
にこっと笑うと、見晴はもう片方の輪っかも解いて、ポニーテールに結い直し始めた。
沙希は、その髪飾りをちょんと触ると、おずおずと笑みを浮かべた。
「うん、ありがとう」
と、ノックの音がした。
「あ、はい……」
「虹野さん、いいかな?」
「え?」
その声を聞いて、沙希よりも先に見晴がすっとんきょうな声を上げた。慌ててあたふたしたあげくに、ちょうど開いていたロッカーに飛び込んで、自分で蓋を閉める。
それと同時にドアが開いて、主人公が入ってきた。
「や、虹野さん」
「主人くん、来てくれたんだ……」
沙希は、ぱっと顔をほころばせた。
「ああ。いつも応援してもらってるからね、今日はこっちが応援する番だと思ってさ」
公はそう言うと、時計をちらっと見た。
「もうすぐだね」
「うん。あ、あのね……」
沙希は赤くなって俯いた。
「一つだけ、お願いしてもいい?」
「え? 何だい?」
「ちょっとだけ……、手を握って欲しいの」
「う、うん」
公はうなずくと、おずおずと差しだされた沙希の手をぎゅっと握った。
その瞬間、後ろで見ていたみのりの額に#マークが浮かび、さらにその後ろのロッカーの中から“ゴン”という音が聞こえたが、二人ともそれには気付かなかった。
「……ありがとう」
沙希は顔を上げた。そして微笑んだ。
まだ憔悴の色は濃かったが、そこに浮かんでいるのは、いつもの沙希の笑顔だった。
「主人くん、あたし、頑張るね!」
「ああ、頑張れ」
「もう、いつまで握ってるんですか!」
みのりが割り込んで、公の手をぺしんと叩いた。それから沙希に言う。
「ほら、虹野先輩! そろそろ着替えないと、時間ですよ!」
「うん、そうだね」
「主人先輩、ほらさっさと出ていって下さいっ!」
ぴっとドアを指さすみのりに、公は苦笑して立ち上がった。
「それじゃ、俺は応援席にいるから」
「うん」
沙希はうなずいた。
「はいはい、さっさと出るっ!」
「お、おいおい、わかったって」
みのりに押し出される公だった。
その公と入れ違いに、ゆかりがすっと控え室に入っていこうとした。公が声を掛ける。
「あ、古式さん」
「まぁ、主人さん。どうなさいました?」
にこっと笑って聞き返すゆかりに、公はポリポリと頬を掻きながら、言った。
「虹野さんのこと、よろしく手伝ってください」
「はい。微力ながら、お手伝いさせていただきます」
ゆかりはうなずくと、控え室に入っていった。
パタン
静かに閉ざされたドアに、公は呟いた。
「……がんばれよ」
 ザワザワザワ
ザワザワザワ
校庭に、突如出現した屋外型台所、“キッチンスタジアム”。
その名に相応しく、闘技場を模して作られた擂り鉢状の観客席。その底には、中央から見て左右にほぼ対称に作られた2つの台所がある。
その台所から正面を仰ぎ見ると、ステージ、そしてその背後に大きな沙希の肖像画が掲げられている。
反対方向には、“キッチンロード”と呼ばれる道があり、入場門に通じている。挑戦者はそこから入ってきて、鉄人沙希の肖像画を仰ぎ見ることになるわけだ。
既に、周囲の観客席はほぼ満席状態だった。数多くの観客達が、ある者は期待に目を輝かせ、ある者は予想を声高に論じあっている。
とはいえ、挑戦者がまだ判らない現在、予想も立てようがないのが実状なのであるが。
中央のステージからやや下がった、それでもまだキッチンを見渡す高さに作られた実況席に、夕子が入ってきた。お上りさんよろしく、キョロキョロ辺りを見回している。
「わぁ、超本格的ぃ!」
「まぁ、伊集院くんのやってることだからねぇ」
続いて入ってきた、こちらは対照的に落ちついている晴海。
スタッフの一人が、夕子に向かって時計を指す。夕子はうなずいた。
「わーってるってばぁ。んじゃ、センセ、始めるよ!」
「いつでもどうぞ」
心得た風に、晴海はうなずいた。
夕子もうなずくと、マイクを握った。そして叫ぶ。
「ニューヨークに、行きたいかぁ!!」
しぃーーーーーん
静まり返るキッチンスタジアム。
晴海は一言、静かに告げた。
「朝日奈さん、思いっ切り外したわね」
《続く》

 メニューに戻る
メニューに戻る
 目次に戻る
目次に戻る
 前回に戻る
前回に戻る
 先頭へ
先頭へ
 次回へ続く
次回へ続く
![]() 喫茶店『Mute』へ
喫茶店『Mute』へ
![]() 目次に戻る
目次に戻る
![]() 前回に戻る
前回に戻る
![]() 末尾へ
末尾へ
![]() 次回へ続く
次回へ続く