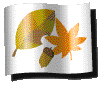喫茶店『Mute』へ
喫茶店『Mute』へ
 目次に戻る
目次に戻る
 前回に戻る
前回に戻る
 末尾へ
末尾へ
 次回へ続く
次回へ続く

沙希ちゃんSS 沙希ちゃんの独り言
第

 話
話
転校!?

もうすぐ12月になろうかっていうある日。
遅くなって帰ってきたお父さんが、お母さんとあたし達……あたしと葉澄ちゃんを呼んだの。
「なんですか、あなた?」
お母さんに聞かれて、お父さんは頭を掻いた。
「いや、実はな、急な話で悪いんだが、今日、本社勤務の辞令が降りてな」
「まぁ、本当? おめでとう」
「よかったね、お父さん!」
「おめでとうございます、お父さま」
あたし達は口々におめでとうって言ったの。きらめき支社から本社にってことは、栄転ってことだもんね。
でも、あたしの喜びは、次のお母さんの言葉でどっかに飛んで行っちゃった。
「それじゃ、東京に引っ越すことになりますね」
「そういうことなんだ」
「……え?」
その瞬間、あたしの頭の中は真っ白になっちゃった。
東京に引っ越すって事は……、東京からきらめき高校に通えるわけないから、そうなると、転校するってこと……になるのよね?
それじゃ、ひなちゃんや彩ちゃんや館林先生やサッカー部のみんなや、……それに、主人くんとも、お別れってこと?
「いつ引越なんですか?」
「一応、辞令は来年から本社勤務ってことだから、今年中ってことになるかな」
「そうですか。それじゃ、年末にかかるんですね」
「年越しは引っ越してからってことにしたいな」
「……いや」
「え?」
お父さんとお母さんが、同時にあたしを見た。
あたしは首を振った。
「転校……したくない」
「沙希……?」
怪訝そうな顔をするお父さん。
あたしは、立ち上がって、叫んでた。
「あたし、転校なんてしたくない!」
「お姉さま……」
葉澄ちゃんが、心配そうにあたしを見上げてる。
「沙希、落ちついて……」
お母さんが何か言いかけたけど、あたしはそのまま居間を飛びだしてた。
 トントン
トントン
ノックの音がする。
「お姉さま、葉澄です」
「……」
あたしが返事をしないでいると、ドアが開いた。
廊下から差し込んでくる光の中に、葉澄ちゃんが立ってる。
「……電気、つけますね」
パチン
微かな音を立てて、蛍光灯がつく。
あたしは、ベッドにもぐり込んだまま、葉澄ちゃんにも背中を向けた。
「……お姉さま……」
葉澄ちゃんは、ベッドのはしに腰掛けた。
「東京に行くの、嫌なんですか?」
「……ってる」
「え?」
「わかってるの」
あたしは、葉澄ちゃんに背中を向けたまま、呟いた。
「あたしのわがままだってことくらい、わかってるの。でも……でも、自分でも、どうしようもないんだもの」
「お姉さま……。わかりました」
ふわっと、毛布の上から、葉澄ちゃんはあたしに抱きついてきた。
耳元で囁く。
「私は、何があってもお姉さまの味方ですから」
「葉澄ちゃん……」
 翌朝。
翌朝。
台所に降りていくと、お母さんが朝ご飯の支度をしてたの。
「あ、沙希。おはよう」
「……おはよう」
「あのね、沙希。昨日のことなんだけど……」
「……お母さん。あたし、絶対東京には行かない」
「沙希……」
「ごめんなさい。でも、決めたの」
「決めたって……。それじゃ沙希は、お父さんに東京に行くのを止めて、ずっときらめき支社にいてって言うの?」
「それは……」
「それとも、お父さんに東京に単身赴任してって言うの?」
「……」
あたしが黙ってると、お母さんはため息を一つついた。
「お父さん、元々は本社に勤めてたの、知ってるわよね? それが、いろいろあってきらめき支社に来てから、もう15年もたったの。お父さんにとっては、本社に戻れる最後のチャンスかも知れないのよ」
「でも、だけど……」
「沙希、私は母親として、あなたの味方をしてあげたい。あなたの言いたいことだってよくわかってるつもりよ。でも……あなたの母親であると同時に、私はあの人の妻なのよ」
静かに言うお母さん。
「沙希とあの人が対立して、どちらかに付けって言われたら、私はあの人に付く。沙希……」
「もういい!」
あたしは、テーブルを叩いた。乗っていたお皿が、ガシャンと音を立てる。
「それ以上は聞きたくない! もう黙ってて!」
「沙希……」
お母さんは悲しそうな目をしてあたしを見ると、その後は何も言わなかった。
 「おはよ、沙希。……どしたん? なんか暗いね」
「おはよ、沙希。……どしたん? なんか暗いね」
「……うん」
お昼休み。食堂でパンをもそもそと食べてたら、ひなちゃんが後ろからあたしの顔を覗き込んだ。
「なんか、鉄人やる直前みたいじゃん。なんぞまた悩みでもあるん?」
「ちょっとね」
あたしが答えると、ひなちゃんはいそいそとあたしの前に座ったの。
「なになに、どーしたの?」
「うん……」
このひなちゃんとも、お別れなのかな?
そう思ったら、なんだか涙がにじんできた。
「さ、沙希、ちょっと、マジにどしたんよ?」
「う、うん、なんでもないよ」
あたしは袖で涙を拭って、笑って見せた。
「大丈夫、だから」
「大丈夫って、ちょっと、マジになんかあったの?」
「大丈夫だってば」
あたしがそう言うと、ひなちゃんはため息を一つついた。
「ん、わーった。でもさ、ホントに何かあるんなら、教えてよね」
「……ありがとう」
あたしは、小さく呟いた。
 「虹野先輩、ここはこれでいいんですか?」
「虹野先輩、ここはこれでいいんですか?」
瑠美ちゃん……新しく入ってきたマネージャーの谷巣さんは、意外とあっさりとサッカー部に溶け込んでくれたの。
ただ、気になるのが茂音くんとの間なのよね。なんだか二人とも妙に避けあってるみたいな気がするの。気のせいとは、思うんだけど。だって、二人とも幼なじみだっていうし。
その瑠美ちゃんは、今はあたしの隣で帳簿をつけてるの。瑠美ちゃんって、ホントにのみ込みが早くてすごいのよね。
「どれどれ……。うん、いいわよ」
「よかった」
そう言って、はにかむように笑う瑠美ちゃん。
早乙女くんに聞いたら、1年の間でも人気赤丸急上昇だって言ってたけど、なんとなくわかるなぁ。
みのりちゃんとも仲良くやってくれてるし。
パタン
「虹野先輩! ボール出しておきましたぁ!」
ちょうどそこにみのりちゃんが戻ってきたの。
「ご苦労様。あ、そこにお茶入れてあるから、喉が乾いてたら飲んでもいいよ」
「はぁい」
そう言ってお茶をゴクゴク飲んでから、みのりちゃんはふとあたしを見たの。
「虹野先輩、何か心配でもあるんですか?」
「え? どうして?」
「さっきから、時々ため息ついてるから……」
「そ、そう?」
あたし、自分でも気付いてなかったのに。無意識にため息ついてたのかな?
「はい。それに、……なんだかすごく哀しそうな目で……」
みのりちゃんはそう呟くと、笑顔になった。
「やだな。私ったら何わけのわかんないこと言ってるんだろ」
「みのりちゃん……。あのね、あたし……」
「あ、虹野先輩! 予備のボール、もうないですよ」
みのりちゃんはロッカーを開けて声を上げた。そして振り返る。
「今度の日曜、空いてますか?」
「え? えっと、うん……」
「それじゃ、備品を買いに行きましょうよ。瑠美ちゃんも行くよね?」
「はい」
瑠美ちゃんはにこっと笑ってうなずいた。
 そして、日曜日。
そして、日曜日。
家じゃあれから冷戦状態。あたし、お父さんやお母さんとろくに口きいてない。
このままじゃダメだってわかってはいるんだけど……。でも、どうしていいのかわかんない。
今日も、何も言わずに出て来ちゃった……。
 「あ、虹野先輩! ここのボール安いですよ!」
「あ、虹野先輩! ここのボール安いですよ!」
「そ、そう?」
あたしは、みのりちゃんの手にしたボールを見て、軽くうなずいた。
「秋穂さん、ちょっとそれ見せて」
瑠美ちゃんはそのボールを軽くトントンとついてみて、言ったの。
「だめよ、秋穂さん。これ、すぐ破れますよ」
「どうしてよ?」
「ついたときの音でわかりますよ。それに、いくら練習用っていっても、あんまり安いボールばっかり揃えても、いざ試合の時になってボールが違うと、とまどいが出るかも……」
「そっかなぁ?」
首を傾げるみのりちゃん。
瑠美ちゃんって勉強してるんだなぁ。
あたしが感心してると、不意に瑠美ちゃんがあたしの後ろに隠れた。
「瑠美ちゃん?」
「黙ってください」
小声で言う瑠美ちゃん。
あたしは後ろを振り返った。なんだ、茂音くんと沢渡くんじゃない。
「あら、沢渡のやつじゃない」
みのりちゃんは苦笑混じりに言った。みのりちゃんがサッカー部に入ったそもそものきっかけって、沢渡くんに誘われたからなのよね。
向こうもあたし達に気付いたみたい。沢渡くんが大きく手を振った。
「おーい、秋穂……」
声がしりすぼみに消えたのは、みのりちゃんが怖い顔でずかずかっと近づいていったから。
「沢渡くん、大声で叫ばないでよ! 恥ずかしいじゃないの!!」
……みのりちゃんの方が大声なんだけどな。
「どうしたの、二人とも?」
あたしが声を掛けると、茂音くん、なぜか直立不動になって答えたの。
「は、はい。えっと、ちょっと買い物に……」
「茂音、お前固いぞ」
沢渡くんが言って、思わずみんな笑っちゃった。
茂音くんは、それから初めてあたしの後ろの瑠美ちゃんに気付いたみたい。
「あ、なんだ。谷巣も来てたのか」
「……私だって、マネージャーだもの」
小さな声で言う瑠美ちゃん。
何となく気まずい空気が流れる。ここは、うん。あたしが一番年上だもんね。
「そういえば、そろそろお昼ね。沢渡くん達、お昼はどうするの?」
「いえ、まだ何も決めてないです」
「そう? それじゃ、一緒に食べない?」
「ええーーー?」
思いっ切り嫌そうな声をあげたのはみのりちゃん。もう、しょうがないなぁ。
あたしは小声でみのりちゃんに囁いた。
「みのりちゃん、ここは我慢してくれないかな?」
「……わかりました。虹野先輩のためですから、我慢します」
小さな声で答えると、みのりちゃんは笑顔になった。
「それで、何を食べるんですか? 型式不明武装多脚砲台みそ汁お新香付きですか?」
「なんなの、それ?」
 結局あたし達は、デパートの最上階の洋食屋でお昼ご飯を食べることにしたんだけど……。
結局あたし達は、デパートの最上階の洋食屋でお昼ご飯を食べることにしたんだけど……。
「うまいうまい」
「まったくだなぁ」
「もう、二人ともそんなにガツガツしないでよ、みっともない」
「秋穂こそ、……あ、俺のエビフライを取るな!」
「なによ、最後まで残してるから、嫌いじゃないのかなって思ってもらってあげたのに」
「俺は一番好きなものは最後まで残しておく主義なんだ」
茂音くんがキッパリというと、瑠美ちゃんが「昔っからそうだよね」って言うような笑みを漏らしてる。
「秋穂さんって、エビフライ好きなんですか? なら俺のも……」
「あのねぇ、いくらなんでも3つは食べられないわよ。そんなにいらないんなら茂音くんにあげたらいいじゃない」
「茂音にはやらん」
「けち」
でも、元気よね、みんな。うんうん。
「虹野先輩」
不意に沢渡くんがあたしに尋ねた。あら、茂音くんが沢渡くんを引っ張ってる。
「やめろって」
「いいじゃねぇか。お前のためなんだから」
「おまえなぁ、ちょっと待てって」
「何なの、二人とも?」
聞きにくいことなのかな?
「それがですねぇ」
沢渡くんが身を乗り出したところを、茂音くん、沢渡くんの頭を上からテーブルに押しつけた。
「いーから黙ってろ。あ、虹野先輩、何でもないですから、何でも。あははは」
「いーかげんにしなさい、あんた達! 虹野先輩が迷惑してるでしょうが! 漫才するなら屋上の野外ステージでやんなさい!」
みのりちゃんがテーブルを叩いて勢いよく立ち上がった。
「みのりちゃん! ちょっと、やめなさい」
「でも、虹野先輩……」
「秋穂さん、虹野先輩困ってますよ」
瑠美ちゃんが言ってくれて、みのりちゃんはやっと落ちついて座ってくれたの。
 「それじゃ、俺達はこれで。ご馳走様でした」
「それじゃ、俺達はこれで。ご馳走様でした」
駅前で、これからゲームセンターに行くっていう沢渡くん達と別れて、あたし達は電車に乗って帰ることにしたの。
「ほんとに、あの二人のせいでとんだ目にあったわ、もう」
スポーツバッグを両手で提げて、ぷんぷんしながら歩くみのりちゃん。
「でも、楽しかったじゃないですか」
瑠美ちゃんはにこにこしてる。
こんな風に歩くことも、もうないかも知れないんだなぁ……。
あたしは、空を見上げた。
冬の空は、今のあたしの心と同じ、灰色だった……。
《続く》

 メニューに戻る
メニューに戻る
 目次に戻る
目次に戻る
 前回に戻る
前回に戻る
 先頭へ
先頭へ
 次回へ続く
次回へ続く
![]() 喫茶店『Mute』へ
喫茶店『Mute』へ
![]() 目次に戻る
目次に戻る
![]() 前回に戻る
前回に戻る
![]() 末尾へ
末尾へ
![]() 次回へ続く
次回へ続く![]()